政策本会議
第103回政策本会議
「潤日(ルンリィー):中国新移民は日本をどう変えるか」
メモ
2025年3月26日
東アジア共同体評議会(CEAC)事務局
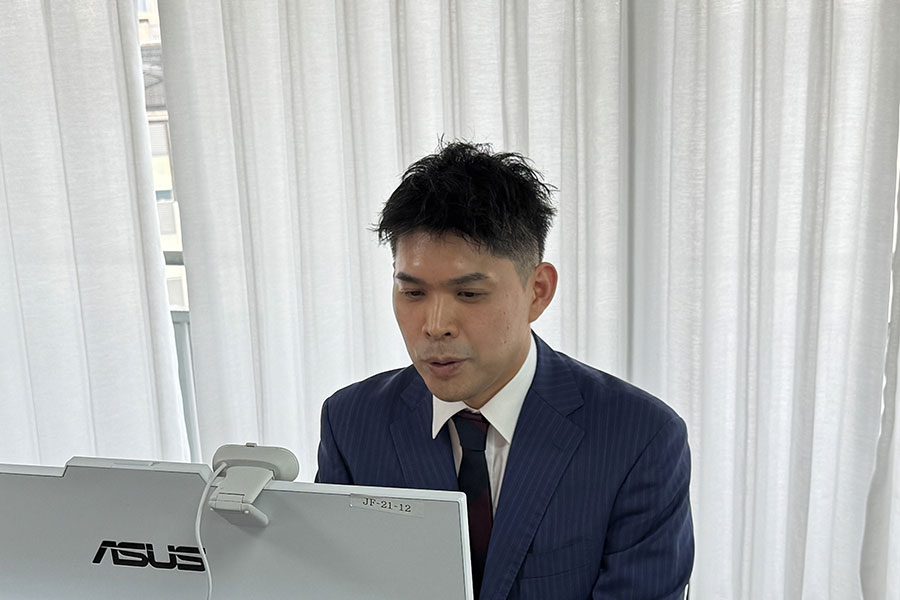
第103回政策本会議は、舛友雄大中国・ASEAN専門ジャーナリストを報告者に迎え、「潤日(ルンリィー):中国新移民は日本をどう変えるか」と題して、下記1.~6.の要領で開催された。
- 日 時:2025年3月26日(水)16時より17時30分まで
- 開催方法:日本国際フォーラム会議にて対面およびZOOMウェビナーによる併用
- テーマ:「潤日(ルンリィー):中国新移民は日本をどう変えるか」
- 報告者:舛友雄大中国・ASEAN専門ジャーナリスト
- 出席者:79名
- 審議概要
(1)「潤(ルン)」の概念と中国新移民の登場
「潤(rùn)」とは中国語で「逃げる」「移住する」という意味を持ち、2022年の上海ロックダウンを契機に流行語となった。発音が英語の「run」に似ていることから、「逃避的移住」というニュアンスが込められている。特に富裕層を中心に、このルン現象は米国に限らず、シンガポール、タイなど世界的なメガトレンドとなりつつあり、日本ほそのスイートスポットであり、日本に「潤(rùn)」する新移民を「潤日」と称している。
(2)中国人が日本を選ぶ理由
中国新移民が日本を選ぶ理由は多岐にわたる。第一に、円安の進行とインフレ率の低さにより、日本は先進国の中で生活コストが比較的安価である。第二に、日本は地理的に中国に近く、航空便も多いため、リモートワークを活かしつつ中国との行き来がしやすい。第三に、アメリカでの反中感情やアジア系ヘイトの高まりと対照的に、日本は安全で政治的安定性が高いとみなされている。第四に、日本では他国と異なり、投資家ビザの緩和・拡大が続いており、中国人富裕層にとって移住のハードルが低い。さらに、漢字文化圏であることから、日本語を完全に習得せずとも生活が可能であり、日本文化への親しみや観光経験も後押しとなっている。
(3)中国新移民の属性と特徴
近年の中国新移民(潤日)の特徴は、従来の技能実習生や留学生とは大きく異なる。彼らの多くは北京・上海・深圳・香港といった都市圏からやって来るアッパーミドル層から超富裕層であり、企業経営者、専門職、文化人、メディア関係者などが目立つ。東京都心のタワーマンションや高級住宅に居住し、1億〜2億円以上の資産を有する者も少なくない。日本語を話せない者も多いが、それでも日常生活を問題なく送ることができている。こうした人々は中国政府との心理的距離を持ち、「サバイバル型移民」ではなく「ライフスタイル重視型移民」としての色彩が強い。
(4)社会的インパクト
中国新移民の最大の社会的影響は教育分野に現れている。都内のインターナショナルスクールでは中国人家庭からの入学希望が殺到し、定員の3割以上を中国系生徒が占める例もある。地方の高校や大学院でも中国人留学生が急増しており、特に米国の大学を卒業後、日本の大学院に進学するという新たな流れも形成されている。背景には米国でのビザ取得困難や就職難がある。
さらに、学区制度を意識し文京区やさいたま市浦和区といった「日本版・学区房」に移住する中国人家庭が増加している。書店、インディペンデント映画、音楽、スタンドアップコメディなど、文化面でも東京を中心に「知識人クラスタ」が形成されつつあり、中国語書籍を扱う独立書店が急増している。
(5)政治的インパクト
白紙運動を契機に、日本に移住してくる中国人リベラル知識人の数は増加している。東京ではセミナーや集会が活発に行われ、往年の北京や香港に似た知的ネットワークが出現している。また、中国出身者が日本の地方政治に参加する動きも始まっている。たとえば徐浩予氏は熱海市長選出馬を表明しており、地方自治体において中国系市議が誕生する事例も見られるようになってきた。
(6)経済的インパクト
湾岸エリアの新築タワーマンション、都心の3A(赤坂・青山・麻布)の高級住宅地では、中国人による不動産取得が顕著である。首都圏郊外や地方リゾート地では「爆建て(ばくだて)」と呼ばれる中国系ディベロッパーによる開発が進んでいる。中には地下銀行を通じて巨額の資金が送金されており、マネーロンダリングとの線引きが困難なケースもある。
不動産以外にも、中国人投資家は酒造、美容整形、幹細胞医療、大学、スポーツチーム(Jリーグ)、ゲームIPなどの買収を試みている。また、「アジア企業」や「シンガポール企業」と名乗ることで、警戒感を回避して日本市場に参入するケースも増加している。
さらに、CFC(Copy From China)型スタートアップとして、AIやテクノロジー分野で起業する中国系人材も増加中である。日本側でもディベロッパー、金融、教育機関などが彼らをターゲットとしたサービス開発に乗り出している。
(7)今後の論点と展望
現在、日本には数万〜10万人弱の潤日が在住しており、その存在はすでに経済・社会・政治において桁違いのインパクトを与えつつある。今後の注目点として、不動産投資規制の強化(例:神戸市の空室課税案)、ビザ政策の見直し、中国の政治経済情勢の変化などが挙げられる。
米中対立が激化する中で、日本は「バッファーゾーン」としての戦略的位置づけを求められている。また、潤日が今後、経済・政治の分野でどのように「日本社会のエリート」として統合されていくのかも、大きな焦点である。とりわけAI研究や先端技術分野では、中国出身者の割合が高く、排除が現実的でない中、日本は共存と活用のあり方を模索することが必要である。
以上
文責:事務局
